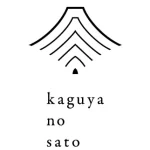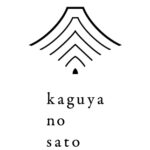東日本大震災の記憶と防災への想い 終活の豆知識76
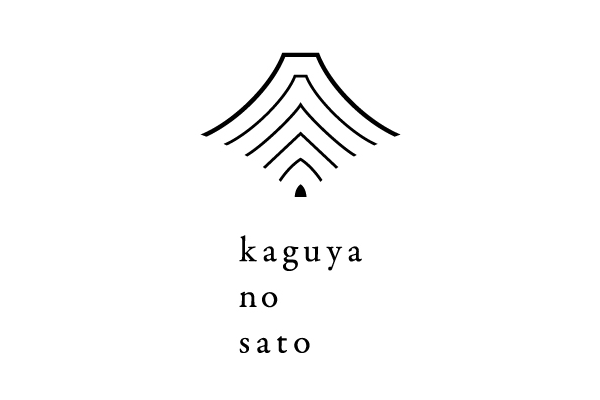
東日本大震災の記憶と防災への想い
本日3月9日は富士市津波対策訓練日となっております。今回の終活の豆知識は東日本大震災の復興現場で葬祭業従事者として奮闘したかぐやの里メモリーホールの中村雄一郎さんの体験をお伝えします。中村さんは震災発生後に現地に入り、ご遺体の搬送業務を中心に、がれき撤去や支援活動に従事しました。その経験から得た教訓や想いを伺いました。

震災直後の現場で
東日本大震災が発生したのは2011年3月11日。被災地は未曾有の被害に見舞われました。震災から約1か月後、仙台市に本社を持つ東北最大手の葬儀社である清月記さんから応援要請があり、私は現地へ向かうことになりました。
震災直後の現地は混乱状態で、救助活動が最優先されていたため、葬祭業者の受け入れ体制が整うまでには時間がかかりました。ようやく葬祭業者の応援が求められるようになり、私たちは被災地で亡くなった方々を火葬場へ搬送する役割を担いました。
出発前、トラックには支援物資とともに、できる限り多くの棺を積み込みました。現地では犠牲者は数万人に及び、棺の数が圧倒的に足りない状況でした。我々は種類問わずより多くの棺を集めて現地に向かい、現地では葬儀ホールを利用し、ひたすら棺の組み立てを行いました。それは交代で夜通し続けられました。

ご遺体搬送と身元確認
現地では警察の要請を受け、学校の体育館などに設けられた安置所から火葬場への搬送を担当しました。ご遺体は、身元が判明した方から順番に近隣の火葬場へと送られました。
身元確認には時間がかかります。発見場所や衣服の特徴などを手がかりに調査が進められますが、時間の経過とともに判別が難しくなります。その情報は各安置所の入り口に張り出されています。行方不明の家族を探す方々がそれらを毎日のように確認に来るのです。そしてご遺体が身元判明し、ご家族のもとへ引き渡されます。やっと見つかった家族はもちろん深い悲しみがありますが、対面した際には、「見つかってよかった」という安堵の表情が見られました。
火葬場は被災地周辺だけでは対応しきれず、多くが他県の施設を利用しました。2時間以上かけて移動することもあり、その間、ご家族の方々とさまざまなお話をしました。震災発生時の状況や、現在の生活について語る方も多く、私はただ静かに耳を傾けることしかできませんでした。この経験を通じて、「家族に見守られながら最期を迎えること」や「家族に見送られる葬儀ができること」は決して当たり前ではないと痛感しました。被災によって突然、大切な人を失った方々に対し、私にできることは少なかったかもしれませんが、せめて火葬場へ向かうその時間だけでも寄り添いたいと思いました。

首都圏との広域連携
震災からしばらく経つと、首都圏の火葬場でも被災地からのご遺体を受け入れる動きが始まりました。もともと都内では火葬待ちが慢性的に発生していましたが、震災対応のためにさらに稼働率を上げ、夜間までフル稼働となりました。大規模災害時には、このような広域連携が非常に重要であることを実感しました。
津波被害と防災への関心
私自身、この経験を経て、特に津波被害対策への関心を高めるようになりました。東日本大震災では、津波による被害が圧倒的で、命だけでなく、人々の生活や街全体を奪いました。その恐ろしさを身をもって知ったからこそ、防災への意識を高める必要性を強く感じています。この富士市では、田子地区と元吉原地区が津波被害の想定区域とされています。特に鈴川本町は、そのほとんどが津波浸水区域に指定されており、多くの住宅が被害を受けると予想されています。津波発生時の死亡者数の予測も出ており対策が急務です。私は今年度から鈴川本町の町内会および自主防災会の津波対策メンバーとなり、この地域の防災活動に全面的に協力することを決めました。本日3月9日は富士市の津波対策訓練が実施されます。この機会に、皆様も防災への備えを改めて見直してみてはいかがでしょうか。
震災の記憶を風化させず、次の世代へとつなげることが、私たちにできる最も重要なことかもしれません。