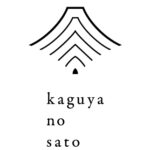急激に変化したお墓事情② 終活の豆知識71
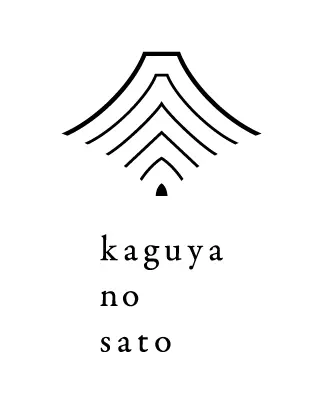
先月に引き続きお墓について、かぐやの里メモリーホールの中村雄一郎さんに伺います。
先月に開催された富士商工会議所主催のまち得ゼミにて最新お墓セミナーを開催したところ、約30名もの参加があり、お墓への関心が高まっていることを改めて実感されたそうです。今月はお墓の種類について伺いました。

お墓の種類
かつてお墓と言えば一般墓であり、多くの方は一般墓を買い求めました。一般墓が持てない方は永代供養墓にするといった、ほぼ2択しか選択肢がありませんでした。それが現在では選択肢が増えて費用も様々な幅が生まれました。(先月号の図解参照)選ばれているお墓の種類を紹介します。
① 樹木葬
シンボルツリーや草木を墓標代わりにしてその周辺に納骨するお墓を樹木葬と呼びます。
日本では歴史が浅い樹木葬ですが、近年は急増しており先月も紹介したように人気ナンバー1のお墓です。平成11年に岩手県の長倉山知勝院で故人の遺骨近くに樹木を植えたのが樹木葬の始まりと言われております。
お墓のサイズや大きさは様々で、樹木がメインで作られているお墓もあれば、石材をメインで作られているお墓もあります。樹木葬に明確な定義はありませんので、好みで選ぶことができます。
(写真1)樹木メインの樹木葬墓地
(写真2)石材メインの樹木葬墓地
現在、富士市には石材メインの樹木葬が多いですが、今後はガーデンタイプの樹木葬も増えてくる予定です。
② 納骨堂
納骨堂は、建物内に遺骨を保管する形式のお墓で室内墓地となります。実は、納骨堂そのものは昭和初期から日本に存在していました。当時の納骨堂はあくまでも一時的に遺骨を預かるための施設でした。富士市では約50年前に富士市中央町の称念寺に初めて100基以上の納骨堂が誕生しました。その納骨堂は富士市初の納骨堂として現在も使われており、近年市内に新たな納骨堂も作られております。近日中に富士市中央町には、最新型の都市型納骨堂もオープンする予定です。納骨堂は、樹木葬と同様に新しく生まれた埋葬の形の一つとして認識されています。
(写真3)富士市中央町にオープン予定の最新型納骨堂
一口で納骨堂といっても、たくさんの種類があります。主なものとしては以下です。
■ロッカー式
ロッカー型の区画が集合しています。(岩本山にある弥勒の丘など)
■仏壇式
納骨場所に各仏壇スペースがあります。(称念寺納骨堂など)
■直接参拝式(自動搬送機械式)
各遺骨が運ばれて参拝できます。(富士市には無く都心部に多数あります)
■間接参拝式(デジタル参拝)
納棺室の手前で参拝してモニターに写真など投影されます。(富士市中央町に近日オープン)
③ 永代供養墓
永代供養墓とは、大勢のお骨が一緒に納められている共同墓(合葬墓)です。お墓を管理する人がいなくなってからも責任をもって管理供養を行ってくれるお墓です。永代供養墓も様々で一定期間を経て合祀する個別安置型や、最初から合祀する合祀型に分けられます。
(写真4)永代供養墓
④ 散骨
散骨とは、法令に則ったやり方で様々な場所にお骨を撒く供養の形です。法令順守の観点から好きなところで散骨することはできません。あくまでも決まった場所になります。最も認知度が高い散骨は海洋散骨です。陸地から200メートル以上離れた沖合の海上にパウダー状にした遺骨を撒きます。海洋の他には、森林や宇宙などがあります。一定の場所に遺骨を納めるのではなく自然に還すという意味合いがあります。
(写真5)海洋散骨
⑤ 一般墓
一般墓は、お墓といったときにイメージするもっとも伝統的な石塔型のお墓です。以前はお墓というと一般墓のことを指しましたが、最近ではお墓のスタイルが多様化してきたため従来のお墓のことを一般墓と呼ぶようになりました。
(写真6)一般墓

お墓の種類は多様化してきました。富士市でも新しいお墓の形が年々増えております。多様化した理由は、先月も解説した通り「お墓の継承」に課題を感じる方が増えたことが大きな要因です。樹木葬や納骨堂の需要が増えたのもその理由が最も多く、続いて費用面や立地などがあります。まだお墓も持っていない方はもちろんですが、既存のお墓はあるけど今後の継承や管理に不安を感じる方も、納骨先選びは慎重に選んでください。かぐやの里メモリーホールでは、納骨に関してのアドバイザーがおりますので、納骨やお墓選びのことはいつでもご相談ください。
先月はお墓の需要の変化を紹介しました。 ※バックナンバーQR
来月には墓じまいについてご紹介します。(次回は12月8日予定)
出典:「いいお墓」「第14回第15回墓の消費者全国実態調査調査」(株式会社鎌倉新書)